病院・施設
目次
- 1. 老人ホーム、何から考えればいい?
- 2. 老人ホームの種類と特徴をまず把握しよう
- 2-1. ①特別養護老人ホーム
- 2-2. ②介護付き有料老人ホーム
- 2-3. ③住宅型有料老人ホーム
- 2-4. ④サービス付き高齢者向け住宅
- 2-5. ⑤グループホーム
- 3. 老人ホーム選びで失敗しないための5つの視点
- 3-1. ① 介護状態・医療ニーズ
- 3-2. ② 費用
- 3-3. ③ 立地と家族の通いやすさ
- 3-4. ④ 施設の雰囲気・スタッフの対応
- 3-5. ⑤ 入居後の生活
- 4. 実際の見学でチェックしたいポイント
- 4-1. ①見学時の質問リスト
- 4-2. ②パンフレットではわからない“空気感”の見極め方
- 4-3. ③スタッフの態度や入居者の表情をよく見る
- 4-4. ④トイレ・お風呂・食堂の清潔さを確認
- 5. 家族として注意したい“本人の気持ち”への配慮
- 5-1. 本人抜きで決めない
- 5-2. 事前に話し合うべきこと
- 5-3. 「親が嫌がっている場合」はどうする?
- 6. 資料請求・見学・入居までの流れ
- 6-1. 施設の情報収集方法
- 6-2. 見学から契約までのステップ
- 7. まとめ
専門家の回答
老人ホーム、何から考えればいい?
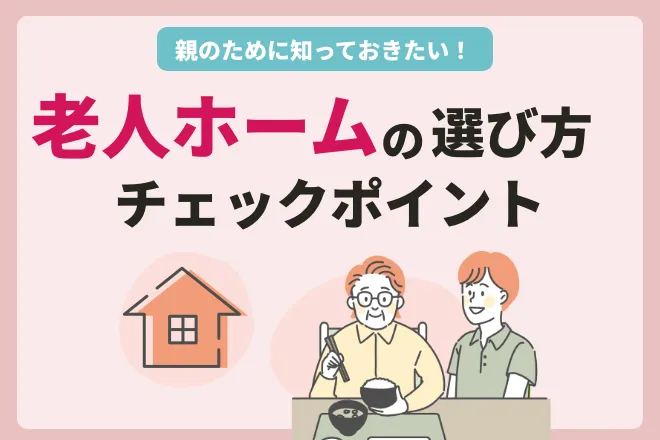
国の方針では、在宅介護が推奨されています。しかし、自宅での介護は仕事との両立もあり負担の大きいものです。「親の介護が心配」と感じたら老人ホームでの生活も選択肢のひとつです。入居を急がないために、早めの準備が必要です。いざという時に、急いで老人ホームを探すと本人や家族の希望を叶える施設を探すことが難しくなります。老人ホームには種類があり、それぞれの老人ホームで特色があります。希望や目的に合った老人ホームを選択するためにも、親御さんが元気なうちに将来についての話し合いや情報収集を進めていきましょう。
老人ホームの種類と特徴をまず把握しよう
老人ホームにはいくつかの種類があります。この章では主な5種類の老人ホームを取り上げ、それぞれの特徴と入居に向いている人を解説します。
①特別養護老人ホーム
介護保険制度に基づいた老人ホームで、通称「とくよう」と呼ばれます。ユニットと呼ばれる10人ほどの生活グループで仕切られることが多く、その他にも個室型の施設もあります。一連の介護サービスがありますが、医療面でのサポートが弱い面がデメリットです。紹介する中では最も費用を抑えられる施設です。
②介護付き有料老人ホーム
民間運営の老人ホームになります。24時間ケアを介護保険サービスで受けることができ、医療サポートもあります。夜間にも介護職員が配備されており、日中は看護師も必ず配備されています。手厚いサービスが大きなメリットです。費用面では、介護サービスがあまり必要でない方はサービス量を調整できないので割高になってしまいます。
③住宅型有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームとの違いは、介護保険サービスを外部から自分で選択する点です。親御さんの状態に合わせて必要な介護保険サービスを自由に選択できます。そのため、介護職員や看護師の配置規定がありません。入居費用などは介護型よりも比較的安価になる傾向があります。
④サービス付き高齢者向け住宅
通称「さこうじゅう」と呼ばれる老人ホームです。賃貸形式の住まいであり介護サービスは外部サービスを利用するか、併設された介護事業所を使用する必要があります。24時間、住宅職員が常駐しており安否確認と生活相談を行います。見守り体制と個室での自由がある施設です。
⑤グループホーム
グループホームは認知症の方が5名から9名のユニットと呼ばれる生活住居で生活する老人ホームです。介護職員が24時間365日の認知症ケアを提供しています。医師の連携や看護師の配備義務はなく、医療サポートが弱いですが手厚い介護や見守りの元生活することができます。
| 施設 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 公的施設の為に費用が抑えられる 24時間体制の介護サービス 終身利用が可能 | 費用を抑えたい 手厚い介護サービスが必要 最後の棲家にしたい |
| 介護付き有料老人ホーム | 24時間体制の介護サービス 特殊浴槽が必ず設置されている 看護師が必ず常駐している | きめ細かい介護が必要な 医療ニーズが高い 入浴を安全に行いたい方 |
| 住宅型有料老人ホーム | 外部の介護保険サービスを利用できる 介護付きより費用が抑えられる イベントやレクリエーションが多い | 介護保険サービスを柔軟に使いたい ある程度自由に生活したい 行事を楽しみたい |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 24時間の安否確認と生活相談が出来る 介護事業所が併設されている 外部の介護保険サービスを利用可能 | 安心して自立生活を送りたい方 近くに相談出来る人が欲しい プライバシーのある生活がしたい |
| グループホーム | 認知症の方が小規模人数で生活する 職員配置が多くサービスが手厚い 外部の介護保険サービスは利用できない | 認知症の方 穏やかに過ごしたい方 多くの介護が必要な方 |
老人ホーム選びで失敗しないための5つの視点
この章では、実際に老人ホームを選ぶ際に失敗しない5つのポイントを紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
① 介護状態・医療ニーズ
親御さんの介護状態によって、適した老人ホームは変わります。ほとんど自立していて、安否確認や少量のサービスであればサ高住、夜間の介護も必要であれば介護付有料老人ホームというように親御さんの状態や介護状態に合った老人ホームを選択しましょう。また、医療サポートが老人ホームによって違うので医療面も合わせて確認が必要です。
② 費用
老人ホームに入居する際は費用の確認が重要です。老人ホームによって入居金や月額費用が異なり、差が大きいです。入居金については特養以外の老人ホームはあります。介護保険サービスなど追加費用が必要になるケースもあるので、下記の一覧表を参考にしてください。行政手続きや理容店の料金が追加でかかる場合があります。
| 施設 | 月額費用 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 13〜15万円 |
| 介護付き有料老人ホーム | 15〜35万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 12〜30万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 10〜40万円 |
| グループホーム | 12〜40万円 |
③ 立地と家族の通いやすさ
老人ホームの立地についても考える必要があります。多くの高齢者にとっては、住み慣れた地域での生活が安心感に繋がる傾向があります。しかし、地域にこだわり過ぎると条件に合った老人ホームを探すことが難しいです。親御様のお住まいに近ければ友人が訪問しやすいです。家族のサポートを優先するのであればご家族のお住まいの近くが良いでしょう。優先事項で老人ホーム選択を行いましょう。
④ 施設の雰囲気・スタッフの対応
老人ホームの雰囲気はパンフレットでは分かり辛い情報です。見学を行い実際に確認しましょう。スタッフ同士の声の掛け合いや表情など、実際に行っているサービスを確認することが大事です。訪問時間は雰囲気が分かりやすい食事時間がおすすめです。大事な親御さんが残りの人生を過ごすことになるかもしれない場所です。住みやすい雰囲気と信頼して任せられるスタッフか確認しましょう。
⑤ 入居後の生活
入居後の生活についても考える必要があります。
食事はどのようなもので、個別に食べやすい形で提供されるか確認しましょう。レクリエーションやイベントが行われることがあるので内容や時期がわかると良いです。
外泊は可能ですが、事前の申請や体調管理など条件があるので外泊の可否と条件について確認しましょう。
実際の見学でチェックしたいポイント
入居前の見学は必ず行いましょう。
準備なく見学訪問すると、知りたかった情報を確認出来ないこともあります。この章では事前準備と見学時のポイントをまとめます。
①見学時の質問リスト
見学の前に質問リストを用意しましょう。
老人ホームを見て回ったり、スタッフとの会話の中では実際に聞きたかった質問を聞けないことがあります。聞き忘れがない様に事前にリストを作りましょう。
事前に重要事項説明書という施設概要を説明した書類を確認できると安心です。職員数などの勤務体制、医療対応が可能か、夜間対応など、事前に不安なことや問題の整理が必要です。
②パンフレットではわからない“空気感”の見極め方
パンフレットでは、設備などの様子は分かっても実際の雰囲気までは分かりません。
入居者の表情やスタッフの表情、におい、室内の音、証明の明るさなどパンフレットでは分からない施設の空気感を確認しましょう。また、訪問時は出来るだけ施設長の説明を受けるようにしてください。老人ホームの顔である施設長から全体の雰囲気を確認しましょう。
③スタッフの態度や入居者の表情をよく見る
サービスの質はスタッフの質でもあります。
スタッフの表情や動き方、コミュニケーションを確認しましょう。スタッフがいきいきと働いていれば良い職場環境の可能性が高いです。働く環境が良くないとスタッフの入れ替わりが多くなり、入居者との関係構築が難しくなります。入居者の表情も見ながら様子を確認しましょう。
④トイレ・お風呂・食堂の清潔さを確認
トイレやお風呂、食堂などの設備の清掃が行き届いているかも確認します。
設備に清掃が行き届いているということは、老人ホーム全体の設備管理がしっかりしているということです。衛生管理が行き届いてないと、感染症などのリスクも上がります。心身ともに安心して生活出来る様に衛生管理が行き届いているかの確認も必要です。
家族として注意したい“本人の気持ち”への配慮
話し合いの過程では本人の気持ちを充分に配慮する必要があります。
この章では話し合いでの本人への配慮について解説します。
本人抜きで決めない
話し合いの過程では、必ず本人と話をしてください。家族だけで話が進んでいくケースが多くあります。本人と家族で話し合いを行い、お互いの希望を擦り合わせましょう。本人抜きで決めた場合、後に大きな不満やトラブルにつながることもあります。
事前に話し合うべきこと
一番最初に今の生活での不安や今後どういった生活を送りたいのかを話し合いましょう。
今の自宅での生活が可能なのか、老人ホームの検討が必要なのかを本人、家族ともに納得した上で話を進めます。提供されるサービスや設備は老人ホームごとに異なっています。現在の不安や課題を洗い出し、何が必要かを整理しましょう。
「親が嫌がっている場合」はどうする?
家族が老人ホームへの入居を望んでも、本人が住み替えを嫌がることは多いです。
家族の都合を押し付けるのではなく、親御さんに安心して過ごして欲しいという気持ちを伝え具体策を話し合いましょう。施設によってはお試し利用をしているところもあります。介護保険サービスを使用しているならショートステイを活用して、まずは短期間の外泊を試してみるのも一つの方法です。少しずつ、自宅外での体験を増やすことが施設入居への練習になります。
資料請求・見学・入居までの流れ
施設の情報収集方法
情報収集はパンフレットでの情報収集が一般的です。
また、情報の相談窓口として地域包括支援センターが設置されています。中学校区ごとに設置されており、介護に関する相談支援を行っているので、気軽に相談することができます。民間の施設紹介業者もあり、各施設の対応状況やサービス内容など、パンフレットでは得られない詳細な情報を提供している場合もあります。
見学から契約までのステップ
見学の後、その老人ホームで良ければ入居申し込みを提出します。
合わせて健康診断書など必要書類を提出し入居審査を受けることになります。必要書類は、健康診断書、戸籍謄本、収入証明など施設ごとに異なるので事前確認が必要です。健康診断書は発行までに1週間ほどかかることがあるので早めに準備しましょう。施設側の審査を待ち、問題がなければ対面での契約、入居となります。入居時には前払い金があるので事前に確認しましょう。
まとめ
ここまで5つの施設を紹介しました。どの施設にも一長一短があり、すべての条件を満たす完璧な施設はありません。自分たちの優先順位を考えて、その希望を満たす施設を選択しましょう。
選択する際は時間がなければ冷静な判断は出来ません。親御さんが元気なうちに将来のことを少しずつ話しましょう。家では暮らせないとなってから施設を探すと、必要な情報がないまま選択を強いられます。元気なうちから将来を見越して早めに情報収集と見学に動きましょう。
自分たちで全ての情報を集め、比較・判断することは簡単ではありません。専門家の意見も取り入れると良いでしょう。身近な専門家として、前章でも紹介した地域包括支援センターがあります。中学校区ごとに設置されているので、近くの地域包括支援センターを探してみてください。専門家の意見を取り入れながら、親御さんが自分らしく生活できる施設を選んでください。
この記事を監修した人
野崎理香 / 正看護師
正看護師として、がん専門センターおよびリハビリ病院に勤務後、訪問看護の現場に従事。
日々のケアを通じて、「本当は聞きたいことがあるのに、時間に追われて質問できない」という利用者様の声に直面し、その課題を解決するため、介護情報サービス「ケアポケ」の立ち上げに参画。
現場での実体験をもとに、看護や在宅ケアに関する実践的な情報提供と記事の監修に取り組む。








この記事にたどり着いたあなたは、「親の生活が心配」「そろそろ老人ホームに入った方が良いのかな」と親御さんの今後の生活に不安を持っているのではないでしょうか。
この記事は老人ホームへの入居を検討されている方に向け、老人ホームの選び方について解説します。