介護
目次
- 1. 介護が必要になったときに使える介護保険とそれ以外の支援
- 2. 介護保険で使える主な6つのサービス
- 2-1. 訪問系サービス
- 2-2. 通所系サービス
- 2-3. 短期入所サービス
- 2-4. 福祉用具レンタル・購入
- 2-5. 住宅改修支援サービス
- 2-6. ケアマネージャーによる支援計画作成
- 3. 介護保険以外で使えるサポート
- 3-1. 医療費助成
- 3-2. 自治体独自の支援
- 3-3. 民間のサービス
- 4. こんな時どうする?シーン別の支援例
- 4-1. 仕事をしながら親を介護したい
- 4-2. 急に入院が決まってしまった
- 4-3. 一人暮らしの親が心配で何かできないか探している
- 4-4. 介護サービスを断る親への対応に悩んでいる
- 5. 介護が必要になったらまずは相談してみましょう
- 5-1. 介護の相談先
- 5-2. 要介護認定の申請手続きとポイント
- 6. まとめ
専門家の回答
介護が必要になったときに使える介護保険とそれ以外の支援

介護が必要になったときに使えるサービスを3つご紹介します。
| サービス名 | 介護保険 | 自治体独自の サービス |
民間サービス |
|---|---|---|---|
| サービス提供者 | 国・自治体 | 市町村 | 民間企業 |
| 対象者 | 要介護・要支援の認定を受けた人 | 各自治体の基準による | 条件なしで利用できる場合もあり |
| 主なサービス内容 | 訪問介護、通所介護、短期入所など | 見守りサービス、配食サービス、安否確認 | 配食サービス、家事代行サービス、見守りサービスなど |
| 費用の目安 | 原則1割、所得に応じて2〜3割 | 無料~一部自己負担あり | 自費 |
| 特徴 | 費用負担を抑えられる | 地域により内容が異なる | 自由度が高く、柔軟に対応できる |
各サービスの詳細をそれぞれ紹介するので、ご覧ください。
介護保険で使える主な6つのサービス
介護保険で利用できる主な6つのサービスを解説します。
訪問系サービス
訪問系サービスは、介護職員が利用者の自宅を訪問し、介護やリハビリをおこなうサービスです。具体的なサービスは以下の通りです。
- 訪問介護
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
提供されるサービス内容は、身体介助や生活援助、リハビリ、医療的ケアなどがあります。
訪問介護では医療行為はできないため、医療行為が必要な場合は看護師が対応する訪問看護の利用が必要です。
夜間や早朝の介護ニーズがある方は、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型のサービスを活用することで、安心して在宅生活を続けられます。
通所系サービス
通所系サービスを見てみましょう。
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリ
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
通所系サービスは、自宅で暮らす利用者が日中に施設へ通い、介護やリハビリを受けるサービスです。
サービス内容は、入浴や食事、排泄などの身体介助に加え、機能訓練やレクリエーションなどがあります。
孤立感の解消や家族の介護負担の軽減の目的でも利用されています。利用者の状況に合わせて最適なサービスを選びましょう。
短期入所サービス
短期入所サービス(ショートステイ)は、自宅で介護を受けている利用者が施設に宿泊して介護や生活支援を受けるサービスです。
ショートステイは介護ケアを受けられる短期入所生活介護と、医療・看護ケアも受けられる短期入所療養介護の2種類があります。
家族の介護負担を軽減させるためにも役立つサービスです。
福祉用具レンタル・購入
利用者の生活に必要な福祉用具のレンタルや購入が可能です。
レンタルや購入の対象となる福祉用具は決まっており、要介護度により利用できる福祉用具が限られる場合があります。
具体例は次の通りです。
- 車椅子
- 杖
- 歩行器
- 手すり(設置できるタイプ)
- 電動ベッド
利用者の負担額は原則1割ですが、所得に応じて2〜3割負担の場合もあります。
住宅改修支援サービス
利用者が自宅でより生活しやすい環境を整えるために住宅を改修する場合に、介護保険が利用できます。
手すりやスロープの設置や開け閉めしやすい扉への取り替え、和式便器から洋式便器への取り替えなどが対象です。
住宅改修の限度額は20万円で自己負担額は1割ですが、所得に応じて2〜3割負担の場合もあります。
住宅改修は原則として1人1回です。
ただし、20万円の上限内に達していない場合や、要介護度が3段階以上重くなった場合などに、2回目以降の利用が認められる場合もあります。
ケアマネージャーによる支援計画作成
ケアマネージャーによる支援計画は、介護が必要な利用者とその家族の状況や、要望をふまえて作成します。
作成する支援計画はケアプランと呼ばれ、介護サービスの利用に必要です。
ケアプランは3種類あり、利用者の状況によって決まります。
- 居宅サービス計画書(居宅ケアプラン)
- 施設サービス計画書(施設ケアプラン)
- 介護予防サービス・支援計画書(介護予防ケアプラン)
ケアマネージャーが利用者と家族から情報収集やアセスメントをおこない、サービス担当者会議で協議しながら決定します。
ケアプランは定期的に見直し、利用者や家族のニーズに合ったサービスが受けられているかどうかを確認しましょう。
介護保険以外で使えるサポート
介護保険を利用する以外にも使えるサポートは以下の通りです。
- 医療費助成
- 自治体独自の支援
- 民間のサービス
医療費助成
医療費助成は、医療機関を受診した際に支払った医療費の一部を負担する制度です。
75歳以上の高齢者と65歳以上で一定の障害がある方は後期高齢者医療制度に加入し、自己負担額は所得に応じて1~3割です。
病院での診察や内服薬、外来でのリハビリ、訪問看護などに利用できます。
訪問看護に医療保険が使える場合がありますが、訪問介護は医療処置を含まないため医療保険の対象外です。
自治体独自の支援
自治体独自の支援には、見守りサービスや配食、安否確認などがあります。
見守りサービスは、日常生活の活動状況を把握するサービスです。
人感センサーや家電を通して利用者の活動量や使用状況を把握します。
利用者の活動が少ないと判断された場合は、職員が訪問したり、家族に連絡が入ったりして安否を確認します。
利用者が緊急事態を知らせることができる緊急通報サービスもあり、ひとり暮らしの方が安心して過ごせるようサポートできる仕組みです。
配食は食事の用意が困難な高齢者に、栄養バランスの整った弁当を配達するサービスです。
弁当を手渡しで利用者に届けるため、安否確認も兼ねられます。
居住する自治体により利用できる業者が異なります。 安否確認は、利用者が無事かどうかを確認するサービスです。
民生委員や地域住民の訪問や電話やはがきにより、利用者の安否を確認します。
民間のサービス
民間のサービスはいろいろな種類があり、利用者に合わせて柔軟に選べる点がメリットです。
具体的なサービスは以下の通りです。
- 配食サービス
- 家事代行サービス
- 見守りサービス
- 安否確認サービス
民間のサービスは介護保険を利用しなくても使えるため、利用者のニーズに合わせて柔軟に選択できます。
庭木の手入れや家の掃除など、介護保険が使えないサービスに活用するのもおすすめです。
デメリットとして、利用するサービスによって金額が高くなる可能性があります。
事前に料金制度を確認しましょう。
こんな時どうする?シーン別の支援例
実際の利用シーン別に、4つの支援例を紹介します。
仕事をしながら親を介護したい
仕事をしながら親を介護する場合は、日中に介護サービスが必要です。
訪問介護や通所介護などの日中に支援が受けられるサービスの利用が適しています。
夜勤や残業の場合や、夜間に介護サービスを利用したい場合は、夜間対応型訪問介護があります。
夜間対応型訪問介護には、定期的にサービスを利用する定期巡回と、トラブル時や緊急時に利用する随時対応の2種類です。
出張などで1泊以上家を空ける場合はショートステイを利用し、施設に宿泊して介護サービスを受けましょう。
急に入院が決まってしまった
介護者が急な入院で家を空ける場合は、ショートステイを利用してみてください。
ショートステイは最大で30日間まで(例外あり)連続して宿泊利用できるため、安心して任せられます。
一人暮らしの親が心配で何かできないか探している
離れて暮らす家族には、見守りサービスや配食の利用がおすすめです。
見守りサービスを通じて家族の状況を把握できるため、安心につながります。
緊急時に備えたい場合は、24時間対応のある見守りサービスを選びましょう。
配食サービスを利用する場合は、安否確認も依頼できる場合があるため、サービス内容を確認してみてください。
介護保険を利用する場合は、利用者の日常生活に必要な支援のみが対象なので、対象外のサービスを受けたい場合は民間サービスを検討しましょう。
通院や買い物の付き添い、家事代行サービスを利用するのもおすすめです。
介護サービスを断る親への対応に悩んでいる
介護サービスを断る親への対応には、以下の方法があります。
- 地域包括支援センターに相談する
- 利用を拒む理由を尋ねる
- 事業所やサービス内容を変更してみる
介護を断る態度の裏には、自信の喪失や介護を受ける恥ずかしさなどの複雑な感情が隠れている場合があります。
家族には話しにくいことも考えられるので、ケアマネージャーに相談して第三者の視点からアプローチしてもらうのも一つの方法です。
介護が必要になったらまずは相談してみましょう
介護が必要になったら、ひとりで抱え込まず相談することからはじめましょう。
相談先や必要な手続きを解説します。
介護の相談先
介護が必要になった場合の相談先は、地域包括支援センターや市町村です。
地域包括支援センターは、介護や医療、保健、福祉などの側面から高齢者を支える総合相談窓口です。
保健師・社会福祉士・主任介護専門員などの専門職で構成され、市町村に必ず設置されています。
高齢者や家族が住む地域で安心して暮らせるために総合的な支援を行っています。
市町村の役所でも、介護や福祉に関わる相談ができます。
介護保険を利用するために必要な要介護認定の申請も、市町村が窓口です。
介護サービスを受けるには、要介護認定を受けておく必要があります。
介護が必要になったときや、日常生活で不安を感じた時点で相談や申請をしておくと安心です。
要介護認定の申請手続きとポイント
要介護認定の申請手続きやポイントを解説します。
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.申請 | 居住地域の市町村の窓口で要介護認定を申請します。 | 主治医意見書の記載を依頼するかかりつけ医を決めておきましょう。 |
| 2.訪問調査 | 本人の自宅に職員が訪問し、調査を行います。 | 身体機能や生活動作、認知機能などの項目があります。 |
| 3.一次判定 | コンピュータを用いて判定を行います。 | 公平な判断を行うため、全国共通の方法で行われます。 |
| 4.二次判定 | 介護認定審査会で判定を行います。 | 主治医意見書と一次判定から判定を行います。 |
| 5.認定通知 | 「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」のいずれかが通知されます。 | 原則30日以内に結果が通知され、結果通知書と被保険者証が届きます。 |
要介護認定の有効期間は、申請の種類により異なります。
新規申請や要介護度の変更申請の場合は、原則として有効期間は6か月ですが、状態に応じて3~12か月の範囲内で設定されることもあります。
身体の状態に変化があった場合は、有効期間内でも変更申請が可能です。
一方、更新申請の有効期間は原則として12か月間ですが、状態に応じて3~48か月までの範囲で設定されることもあります。
要介護認定の有効期限が過ぎると、介護サービスが利用できません。
更新申請は有効期限の60日前から可能です。
市町村から案内が届くので、期限が切れる前に必ず更新申請を行いましょう。
まとめ
介護が必要になった場合は、介護保険によるサービスだけでなく、自治体や民間のサービスも利用できます。
介護サービスを活用することで、利用者の生活を支援したり、家族の介護負担を軽減したりできます。
介護サービスの利用を検討している場合は、地域包括支援センターや市町村の窓口で相談してみましょう。
介護保険によるサービスは、要介護認定が必要になるため、早めの相談が安心につながります。
この記事を監修した人
野崎理香 / 正看護師
正看護師として、がん専門センターおよびリハビリ病院に勤務後、訪問看護の現場に従事。
日々のケアを通じて、「本当は聞きたいことがあるのに、時間に追われて質問できない」という利用者様の声に直面し、その課題を解決するため、介護情報サービス「ケアポケ」の立ち上げに参画。
現場での実体験をもとに、看護や在宅ケアに関する実践的な情報提供と記事の監修に取り組む。







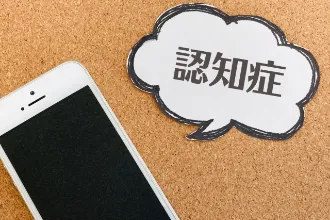
「介護サービスの種類や選び方がわからない」「どうしたら介護サービスを利用できる?」
介護保険やサービスの利用方法などがわからずにお困りではありませんか。
介護サービスにはさまざまな種類があり、利用するには決められた手続きをおこなう必要があります。
本記事では介護保険で利用できるサービスや、介護保険以外で利用できるサポートについて解説します。
介護サービスの利用を検討している方の疑問が解決できれば幸いです。