介護
目次
- 1. はじめに:介護とキャリアのはざまで悩むあなたへ
- 1-1. 親の介護と仕事の責任が重なる40〜50代
- 1-2. 「辞めるしかない」と思う前にできることがある
- 1-3. "働き方を見直す"という選択肢を持つことが大切
- 2. 40〜50代に増えている「介護と仕事の両立」問題とは?
- 2-1. 介護離職が40代後半〜50代に集中している理由
- 2-2. ライフイベント(子育・昇進・住宅ローン)と重なる時期
- 2-3. 両立できなかった人の後悔・失敗談
- 3. 働きながら介護を続けるために必要な"働き方の柔軟性"
- 3-1. 時間・場所・働く量を見直す視点
- 3-2. テレワーク・時短・フレックスなど実際に使える制度
- 3-3. 「今の会社でできること」と「会社を変えるという選択」
- 4. こんな働き方も選べる! 実例から見る"介護と仕事"の両立スタイル
- 4-1. 在宅勤務+ヘルパー併用で親を見守る
- 4-2. 転職して通勤時間を減らした
- 4-3. 介護が落ち着くまで「週3勤務」に切り替えた
- 4-4. 副業・フリーランスを選んだ人のケース
- 5. 仕事をしながら介護を支えるための社会的制度と支援
- 5-1. 介護休暇/介護休業とは?
- 5-2. 働く人のための「両立支援制度」まとめ
- 5-3. 地域包括支援センターやケアマネジャーの使いどころ
- 6. 自分の"軸"を持って働き方を設計するヒント
- 6-1. キャリアの棚卸しと優先順位の見直し
- 6-2. 「収入」「やりがい」をどうバランスするか
- 6-3. これからの人生に介護が与える影響をどうとらえる?
- 7. まとめ:介護も仕事も、あなたの人生の一部だからこそ
- 7-1. "選び方"次第で未来は変わる
- 7-2. 周囲の理解と制度を味方に、無理なく両立を目指そう
- 7-3. 自分の働き方は、自分でデザインしていい
専門家の回答
はじめに:介護とキャリアのはざまで悩むあなたへ

経済産業省の推計によると、2030年に家族を介護しなければならない人は833万人に達し、そのうち、仕事と介護の両立に直面する、いわゆる「ビジネスケアラー」は318万人に達します。これは全労働人口の約5%を占めます。仕事と介護の両立は今後、ビジネスパーソンの誰もが直面する問題なのです。
親の介護と仕事の責任が重なる40〜50代
終身雇用制が必ずしも一般的でなくなった現在でも、日本の企業で40代の社員は課長などの中間管理職、50代は部長など役員に次ぐ働きを求められます。ビジネスパーソンとしては脂の乗った時期ですが、ちょうどその頃、親が前期・後期高齢者となり、会社の仕事、家族の介護の間で責任ある行動を求められるようになります。
自らのキャリアを築くためには、会社の仕事に専念すればいいですが、家族の介護にも時間と神経、そして、資金を割かなければなりません。仕事と介護の両立はビジネスパーソンの生産性低下を防ぐための社会的な課題なのです。
「辞めるしかない」と思う前にできることがある
とはいっても、仕事と介護の両立は甘くありません。介護には時間と資金が必要です。深夜の介助などで寝不足になり、翌日の仕事に支障が出る可能性があります。それを避けるために訪問ヘルパーを依頼したり、老人ホームなどの施設に入居を勧めることができますが、そのためには資金が必要です。
介護離職をすると、介護に回せる資金が少なくなり、ますます自分で介護をしなければならない悪循環が生まれます。介護離職をしてはいけない理由がここにあります。ビジネスケアラーはさまざまなサービスを利用しながら、介護を「マネジメント」する必要があるのです。
"働き方を見直す"という選択肢を持つことが大切
2025年4月施行の改正育児介護休業法では、企業は家族の介護に直面した従業員に対し、介護休暇/介護休業などの制度の周知が義務化され、テレワーク、時短勤務などの実施が努力義務化されました。制度を賢く使いながら、自身の働き方を見直す環境が徐々に整いつつあります。
40〜50代に増えている「介護と仕事の両立」問題とは?
それでは、40〜50代の仕事と介護の両立の問題を個別に見ていきましょう。
介護離職が40代後半〜50代に集中している理由
2025年現在、仕事と介護の両立ができずに、介護離職をしてしまう人は約11万人に上ります。介護離職で一番多い理由は、介護する人自身の健康の悪化です。仕事と介護で板挟みになり、休息も含めた自分の時間が取れなくなって、体調を崩す人が多いのです。仕事と介護を長く続けるためには、会社でも家庭でもない、自分の時間を確保することが必要です。
ライフイベント(子育・昇進・住宅ローン)と重なる時期
40〜50代のビジネスパーソンは介護の他にも、子育てなどさまざまなライフイベントが重なります。特に40代は子どもの教育、進学など、育児、養育とは違う段階に入ります。また、会社では昇進など、収入の増加に伴う責任が求められるようになります。これらの出来事と並行して、住宅ローンを組んで、持ち家を購入する人も出てきます。40〜50代は会社と家庭での責任がともに大きくなるのです。
両立できなかった人の後悔・失敗談
仕事と介護の両立ができず、やむなく介護離職してしまった人の特徴は、制度を上手く活用し、介護を上手くマネジメントできなかったことが挙げられます。
「自分の親の面倒は自分でみたい」気持ちは分かりますが、家族、それも肉親を介護することは想像以上に大変なことです。介護離職するということは、当然、収入を失うので、何か手立てを打たないと、貧困に陥ります。すべての人が親の年金で生活できるわけではありません。
「介護をしていて、一番つらかったのは貧困だった」という声はよく耳にします。家族を介護していても、社会的な責任を投げ出してはいけないのです。
働きながら介護を続けるために必要な"働き方の柔軟性"
会社で働きながら、家族の介護を続けるためには、今までにはない柔軟な発想・視点が必要です。
時間・場所・働く量を見直す視点
今までのように定時出社、8時間労働に加えて残業をしていては、家族の介護をするのは難しいです。仕事と介護の状況に応じて、働く時間・場所・分量を柔軟に変える必要があります。
テレワーク・時短・フレックスなど実際に使える制度
育児介護休業法では、会社は従業員に対して、介護休暇・休業など活用できる制度を周知し、適宜、相談に応じることを「義務」としています。また、仕事と介護の両立のためにテレワーク、時短・フレックス勤務を活用することを「努力義務」としています。介護休暇/介護休業以外に使える施策は、個々の会社で異なりますが、人事担当者に相談し、制度をフルに活用しましょう。
「今の会社でできること」と「会社を変えるという選択」
仕事と介護の両立に直面した際には、まず、会社の人事担当者に相談することが大切です。対話の中で、必要なさまざまな施策が浮き彫りになってくるはずです。職場の理解は欠かすことはできません。その中で、選択肢が少ないと感じたら、仕事と介護の両立に力を入れている会社に転職することも選択肢に入るかもしれません。
こんな働き方も選べる! 実例から見る"介護と仕事"の両立スタイル
会社の仕事に繁忙期と閑散期があるように、家族の介護もいつも忙しいわけではありません。時期に応じて、対処すべきことは変わってきます。仕事をマネジメントするように、介護もマネジメントする必要があるのです。
在宅勤務+ヘルパー併用で親を見守る
家族の介護をする時にまず活用したいのが、介護保険制度です。保険料と公費(税金)で運用される介護保険サービスは、自費サービスに比べて低価格で利用できます。その中でおすすめしたいのが訪問介護です。食事・排泄・入浴の三大介助を住み慣れた自宅で提供してくれます。在宅勤務と併せて活用すれば、介護のプロのヘルパーに介助を任せつつ、自分の仕事に専念できます。
転職して通勤時間を減らした
転職して通勤時間を減らすのもひとつの方法です。通勤時間は1時間を超えると、ストレスが高くなると言われています。通勤時間を短くすることは、介護と自分の時間を確保するだけでなく、自身の健康を守るためにも有効です。
介護が落ち着くまで「週3勤務」に切り替えた
介護も繁忙期と閑散期があります。要介護認定を受ける時、施設に入居する時などは総じて忙しくなります。勤め先の会社に出勤日を調整する制度があれば、介護休暇/介護休業と併せて、活用するのも手です。
副業・フリーランスを選んだ人のケース
介護離職のようなネガティブな理由ではなく、独立・起業など積極的な理由で会社を辞めることも考えられます。ただし、事業の収益化、資金繰りはシビアなので、最初は副業で挑戦するのもいいかもしれません。自宅と職場を近づける、または同じにすることで、仕事と介護を無理なく行えるようになるでしょう。
仕事をしながら介護を支えるための社会的制度と支援
次に仕事と介護の両立を促す制度を見ていきましょう。
介護休暇/介護休業とは?
介護休暇/介護休業は、育児介護休業法に定められた労働者の権利です。対象となるのは、要介護状態の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を持つ労働者です。介護休暇/介護休業は以下のように運用の方法が異なります。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 取得できる日数 | 要介護の家族が1人の場合は年5日 要介護の家族が2人の場合は年10日 |
要介護の家族1人につき3回(通算93日) |
| 手続方法 | 書面のみならず口頭での申請も可能 | 休業開始予定日の2週間前までに書面を通じて事業主に申請 |
働く人のための「両立支援制度」まとめ
介護休暇/介護休業の他にも、仕事と介護の両立支援制度は以下のようなものがあります。これらの制度は育児介護休業法によって、企業が少なくとも1つ以上設けるように定められています。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 時差出勤制度
- 介護費用の助成措置
地域包括支援センターやケアマネジャーの使いどころ
市区町村が社会福祉法人などに運営を委託している、地域包括支援センターには、介護保険サービスの運用のプロである、ケアマネジャー(介護支援専門員)が在中しています。家庭、地域の介護に関する困りごとを行政に繋ぐ役割を果たしているので、家族が要介護認定を受けていなくても、積極的に相談、活用しましょう。また、街場の居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)のケアマネジャーも相談に応じています。
自分の"軸"を持って働き方を設計するヒント
フリーアナウンサーの町亞聖さんは、10年以上、実母・実父を介護してきました。彼女は仕事と介護を両立するためのコツは「自分のライフスタイルを作る」ことだと言っています1。この視点から仕事と介護の問題を考えてみましょう。
キャリアの棚卸しと優先順位の見直し
仕事と介護の両立は、言い換えるならば、自分と家族の共存にほかなりません。ほとんどの人が自分と家族を二者択一できないように、仕事と介護はコインの両面のように、介護が必要な家族がいるかぎり、その人にいつまでも付いてきます。
仕事と介護の両立は究極的には、自分の人生と家族の人生どちらを優先するかという、その人の倫理に委ねられています。その中で今後、自分のキャリアをどのように築いていくのか……。40〜50代でキャリアの棚卸しをして、物事の優先順位を見極めなければなりません。
「収入」「やりがい」をどうバランスするか
仕事と介護の両立において、安定した十分な収入は絶対に必要です。十分な収入があれば、介護を「外部委託」することも可能だからです。仕事も介護も適宜、人に任せる姿勢が大事です。すべてを自分で抱え込む必要はありません。
ただし、その中で、自分は仕事を通じて社会とどのように関わっていきたいか、介護を通じて家族とどのように関わっていきたいか、と考えることが大切です。その結果、収入に還元されない、仕事と介護に豊かなやりがいを見いだせるはずです。
これからの人生に介護が与える影響をどうとらえる?
養育や教育とは違い、介護は必ず終わりがきます。つまり「死」です。そのため、介護を通じて、どれほど家族と関わったとしても、後悔はついてきます。その事実を受け入れつつ、家族の人生を尊重しながら、最終的には自分の人生を優先して生きるしかないのです。
まとめ:介護も仕事も、あなたの人生の一部だからこそ
"選び方"次第で未来は変わる
「あの時こうすれば良かった」。人は皆、晩年に人生の分岐点を省みます。そのひとつが仕事のキャリア、家族の介護であり、介護離職はそのどちらにも確実に打撃を与えます。介護に関する正しい知識を身につけることで、どちらも犠牲にしない、正しい選択をすることができます。
周囲の理解と制度を味方に、無理なく両立を目指そう
昔は家族の介護は世間に隠すべき事と見られていましたが、今は違います。もっと人々にオープンに話していいですし、その姿勢が介護する人/介護される人のQOLを確実に高めます。仕事と介護の両立のためには、職場と地域の人々の理解が必要なのです。
自分の働き方は、自分でデザインしていい
町亞聖さんの言うように、仕事と介護の両立の鍵は、その人のライフスタイルにあります。これが柔軟かつ確固たる人は、自分の良心で物事の価値判断を下すことができます。介護はつらく、大変なイメージがありますが、家族と関わる絶好の機会です。介護を通じて、仕事の意義、家族の関係を問い直してみてください。
出典
- 町亞聖「私の医療・介護物語」『シルバー新報』(環境新聞社、2024年6月14日),2025/04/14
この記事を監修した人
野崎理香 / 正看護師
正看護師として、がん専門センターおよびリハビリ病院に勤務後、訪問看護の現場に従事。
日々のケアを通じて、「本当は聞きたいことがあるのに、時間に追われて質問できない」という利用者様の声に直面し、その課題を解決するため、介護情報サービス「ケアポケ」の立ち上げに参画。
現場での実体験をもとに、看護や在宅ケアに関する実践的な情報提供と記事の監修に取り組む。
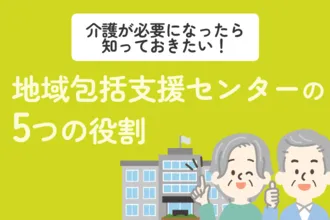
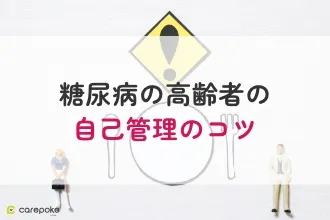
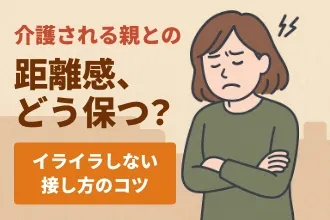





「親の面倒は自分でみたいが収入を失うのは困る」「仕事しながら介護をしているが休息が取れない」
介護と仕事のバランスが取れず悩んでいませんか?
40〜50代は介護の他さまざまなライフイベントが重なり、会社と家庭での責任がともに大きくなる時期でもあるため、時間と資金が必要になります。
本記事では働きながら介護を続けるために必要な考え方、社会的制度をくわしく解説していきます。
介護と仕事の両立でお悩みの方のお役に立てれば幸いです。