介護
目次
専門家の回答
「急に親の介護が必要になった」あなたへ

親の介護は、病気や転倒などによって急に始まることもあります。何も知識がない状態で介護が始まると、誰もが「何から手をつければいいのかわからない」と不安に思うでしょう。
不安を和らげるためには、まず親や家族の状況を整理する必要があります。さらに、介護サービスを受けるまでの流れを知ることも大切です。
不安を一人で抱えこまずに、福祉や医療などの専門家に相談してみましょう。
介護のはじまりは「要介護認定」の申請から
公的な介護サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定とは、日々の生活で介護がどの程度必要か、以下の7段階にわけて判定することです。
介護保険を利用すれば、料金の1割〜3割の自己負担でレンタル、購入できます。
介護保険レンタル、購入は介護保険サービスのひとつなので、利用の際にはケアマネジャーとの連携が必要です。
利用の前には介護保険の申請を行います。
- 要支援1:日常生活の中で支援が必要な状態
- 要支援2:部分的介護を要するが、改善する可能性が高い状態
- 要介護1:部分的介護を要する状態
- 要介護2:軽度の介護を必要とする状態
- 要介護3:中程度の介護を要する状態
- 要介護4:重度の介護を要する状態
- 要介護5:最重度の介護を要する状態
要介護認定の結果をもとに、要支援の方は介護予防サービス、要介護の方は介護保険サービスが利用できるようになります。
要介護認定の流れ
要介護認定の申し込みから結果がわかるまでの流れは、以下のとおりです。
- 介護を受ける親が住んでいる市区町村の窓口に申請する
- 調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態や日常生活について調査する(訪問調査)
- 市区町村が主治医に依頼し、主治医意見書(傷病や心身の状態などに関する意見が記載された書類)を作成してもらう
- 訪問調査と主治医意見書をもとに、コンピューターで一次判定する
- 保健や医療、福祉の専門家が集まる介護認定審査会が二次判定する
- 判定の結果に基づいて要介護度を決定する
- 申請から原則30日以内に申請者へ審査結果が届く
要介護認定は、親本人だけでなく家族が代理で申請することも可能です。
なお、要介護認定を受けるタイミングは特に決まっていません。早めに受けておくと要介護度や介護保険サービスについて知れるため、将来の安心につながるでしょう。
要介護認定の必要書類も踏まえた詳しい流れを知りたい方は、こちらも合わせてご覧ください。
要介護認定を受けるには?介護保険の申請方法や流れを分かりやすく解説
どこに相談すればいい?地域包括支援センターを活用しよう
地域包括支援センターとは、地域の高齢者の暮らしをサポートする総合相談窓口です。ちょっとした悩みや病気のこと、金銭的な問題など幅広い相談ができるため、最初の相談窓口としておすすめです。
地域包括支援センターには介護や保健、福祉などの専門家が在籍しており、問題解決をサポートしてくれます。さらに、医療機関や行政などと高齢者や家族を繋ぐ役割もあります。
なお、地域包括支援センターに相談する際は、親が住んでいる地域を担当する施設にしましょう。地域包括支援センターは、対象地域の医療機関や行政などと協力し、地域に密着したサービスを行うからです。
地域包括支援センターの場所は、厚生労働省のホームページで探せます。あるいは「地域包括支援センター 〇〇(親が住んでいる地域名)」と入力して検索してみましょう。
地域包括支援センターの役割や相談事例について詳しく知りたい方は、こちらも合わせてご覧ください。
要介護認定を受けるには?介護保険の申請方法や流れを分かりやすく解説
ケアマネジャーとは?介護の計画を立てる“案内役”
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、要介護・要支援の方が適切な介護サービスを受けられるようサポートする役割を担っています。
ケアマネジャーの主な役割は、ケアプラン(高齢者が適切な介護サービスを受けるために必要な計画書)の作成です。要介護認定後に高齢者や家族の話を聞き、自立した日常生活を送るために必要な支援の方法や頻度を決定します。
さらに、ケアマネジャーは現状を踏まえて、自宅介護か施設入所のどちらが適しているか提案してくれます。利用できる訪問介護や通所介護(デイサービス)などの情報も教えてくれるため、ケアマネジャーと相談しながら自分たちに合った事業所を探しましょう。
家族として最初に確認すべきこと【チェックリスト形式】
親の介護が急に必要になった際に落ち着いて対応できるよう、家族が確認すべきことがあります。以下のPDFにチェックリスト形式でまとめているため、保存してご活用ください。
自宅での生活について
- 一人で移動できますか
- 一人で外出できますか
- トイレは一人でできますか
- 食事は一人で食べられますか
- 水分を飲むときにむせますか
- 一人で掃除や片付けができていますか
認知機能について
- 同じ話を何度も繰り返しますか
- 曜日や日付をわかっていますか
- 探し物をする頻度が増えていますか
- 料理の味が変わったり、作るのに手間取ったりしていますか
- 趣味や好きなことに興味を示さなくなりましたか
- 物がなくなると誰かに盗まれたと疑いますか
医療的ケアについて
- 定期的に服用している薬はありますか
- 持病はありますか
- 過去の病歴を把握していますか
- かかりつけ医はどこですか
- 保険証や診察券などの保管場所はどこですか
介護の対応方法について
- 親と同居するか通いで介護するか、どちらがよいですか
- 兄弟姉妹がいる場合、介護を分担できそうですか
- 介護と仕事を両立するために利用できる公的な制度(介護休業制度、介護給付制度など)を知っていますか
- 会社独自の支援制度(時間単位の休暇制度、テレワークの導入など)はありますか
費用について
- 介護サービスの費用は誰がどの程度負担しますか
- 親の貯蓄を介護費用に充てられそうですか
- 介護保険サービスを利用した際の自己負担割合はどの程度か把握していますか
- 介護費用の負担を軽減するサービス(特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費など)を知っていますか
在宅介護?施設介護?方向性を考えるためのヒント
在宅介護か施設介護のどちらが自分たちに合っているか判断するためには、それぞれの特徴を理解しておく必要があります。ここからは、それぞれの特徴と選び方のポイントをご紹介します。
在宅介護の特徴
在宅介護を選択すると、親が住み慣れた自宅で生活できます。さらに、生活のルールがある施設と違い、自分のペースを守りながら暮らせる点もメリットです。
一方、介護を担う家族には負担がかかります。介護に多くの時間を費やすようになると、仕事を続けるのが困難になることもあるでしょう。家族の余裕がなくなってくると、親との関係が悪化する恐れもあります。
施設介護の特徴
施設介護は常に専門のスタッフによる見守りがあるため、家族の負担が少なくなります。金銭面での負担は大きいですが、自由な時間が増える点は施設介護のメリットです。
なお、施設介護に対して「親を手放す」というイメージを持つ方もいます。しかし、施設介護は「スタッフと協力しながら親を支える」形に変わるだけのため、決して親を手放すわけではありません。
選び方のポイント
在宅介護と施設介護のどちらを選ぶにしても、ケアマネジャーとよく相談することが大切です。そして、気になる事業所は見学するようにしましょう。
事業所を見学すると、パンフレットやホームページだけではわからない部分も確認できます。事業所の雰囲気やスタッフの様子を肌で感じられるため、自分たちと合っているか判断しやすくなるでしょう。
看護師からのアドバイス:「最初から完璧を目指さなくていい」
介護は「正解」よりも「その人に合う対応」が大事です。親や家族の状態も常に変わっていくため、その都度自分たちに合う対応を模索しながら介護に臨みましょう。
親の介護はいつまで続くかわかりません。そのため、家族だけで対応していると徐々に疲れが溜まっていく恐れがあります。
大切なのは、疲れすぎる前に「外の手」を借りることです。介護や医療などのプロに相談し、早くから情報を集めましょう。
介護の情報があれば、家族だけで無理しすぎる以外の選択肢も選べるようになります。
迷ったら、まず“相談”からはじめてみましょう
急に親の介護が必要になった際は、まず要介護認定を受けましょう。そして、地域包括支援センターへ相談し、ケアマネジャーと連携するのが一般的な流れです。
介護のスタートにおける最大のポイントは、一人で抱え込まないことです。相談できる相手は、地域包括支援センターやケアマネジャーだけでなく、かかりつけ医や看護師などもいます。
福祉や医療などの専門家の力を借りながら、自分たちに合った介護を模索していきましょう。
出典
- 介護予防サービスの種類と費用のめやす(要支援1・2の方)|足立区,2025/9/19
- サービス利用までの流れ | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」,2025/9/19
- 要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省,2025/9/19
- 主治医意見書|埼玉県,2025/9/19
- 地域包括ケアシステム|厚生労働省,2025/9/19
- 地域包括支援センターとは|奈良県,2025/9/19
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)|厚生労働省,2025/9/19
- 認知症?「気づいて相談」|京都市,2025/9/19
- サービスにかかる利用料 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」,2025/9/19
- 仕事と介護 両立のポイント|厚生労働省,2025/9/19
この記事を監修した人
野崎理香 / 正看護師
正看護師として、がん専門センターおよびリハビリ病院に勤務後、訪問看護の現場に従事。
日々のケアを通じて、「本当は聞きたいことがあるのに、時間に追われて質問できない」という利用者様の声に直面し、その課題を解決するため、介護情報サービス「ケアポケ」の立ち上げに参画。
現場での実体験をもとに、看護や在宅ケアに関する実践的な情報提供と記事の監修に取り組む。


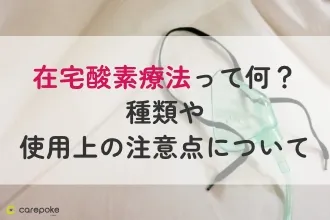


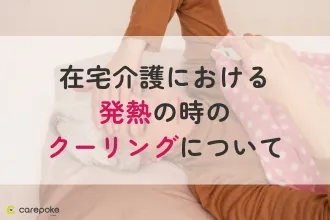
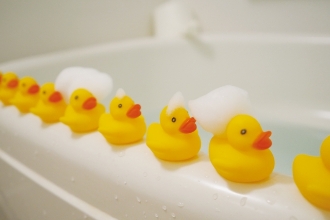
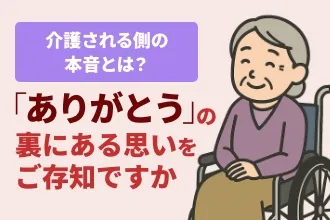
「急に親の介護が必要になり、どうしたらいいのかわからない」
「介護について誰に相談したらいい?」
初めての介護が突然始まり、このような不安を感じていませんか?
急に介護が始まった場合は、一人で悩まずに専門家へ相談することが大切です。
本記事では、介護サービスを受けるまでの流れや最初の相談先、介護の方向性を考えるヒントなどを、現場経験のある看護師がやさしく解説します。
急に親の介護が始まり不安を感じている方の参考になれば幸いです。