介護
目次
- 1. 「子どもが親を介護するのは当然」だと思っていませんか?
- 2. 「親の介護は子の務め」という思いが強くなりすぎると起きること
- 3. なぜ「子が親を介護するべき」と思ってしまうのか?
- 4. 親の介護を最後までやりきりたい気持ちを大切にしながら、現実と向き合うには?
- 4-1. 介護のプロに頼る
- 4-2. 親の「希望」と「必要な支援」を分けて考える
- 4-3. 自分自身の生活と健康も守る
- 5. 「介護の全部」を背負わないためにできること
- 6. 誰かに頼ったからこそ、親子関係が守られた|体験談
- 6-1. 兄に週末の介護を頼ったケース
- 6-2. 介護のプロに頼ったケース
- 7. 親の介護は「務め」から「選択」へ。介護の形に正解はありません
専門家の回答
「子どもが親を介護するのは当然」だと思っていませんか?
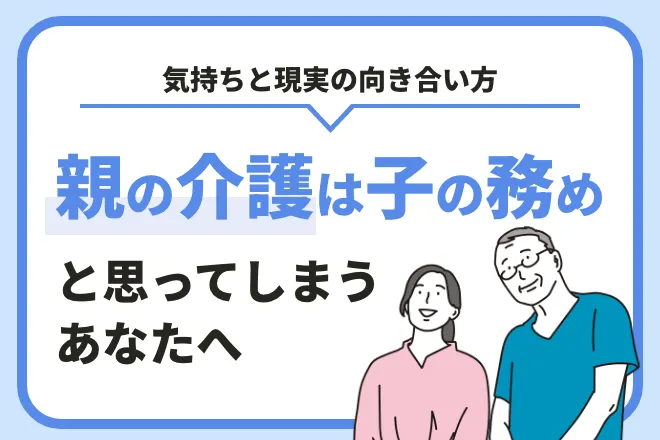
親の介護が必要となったとき、今までお世話になったのでやってあげたいと考える方もいるでしょう。
しかし、介護は身体面だけでなく、精神面や金銭面でも負担がかかります。介護による疲れが蓄積し、気づかないうちにうつ症状を引き起こしていることも少なくありません。
親への感謝だけでは続けられないのが“現実の介護”です。心も体もすり減る前に、一度立ち止まり、現状のまま介護を続けていけるのか考えることが大切です。
「親の介護は子の務め」という思いが強くなりすぎると起きること
親の介護は“子の務め”という思いが強くなると、限界を超えても無理を続けてしまう場合があります。責任感の強さからきょうだいに頼れず、一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
介護が生活の中心となり、自分の人生を後回しにしている状態に罪悪感を覚えることもあるでしょう。
さらに、周りの家族や親から「介護するのが当たり前」と思われるようになり、感謝されない可能性もあります。感謝の言葉がないと、頑張っても報われていないと感じ、傷つくこともあるでしょう。
あなたはすでに十分頑張っています。たまには肩の力を抜いて、自分自身をいたわってあげましょう。
なぜ「子が親を介護するべき」と思ってしまうのか?
子が親を介護するべきと思ってしまう理由の一つに、昔からの家族観・価値観があります。
親が祖父母を介護していた姿を子どものころに見ていると、子が親を介護するのは当たり前と考えやすくなります。親や親族、近所の方から「子が親を介護するのは当然」という目で見られることで、自分が親を介護しなければと強く感じてしまう方もいるでしょう。
さらに、たとえ介護のプロであっても、自分の親を他人に任せるのは「冷たいこと」と誤解している場合もあります。なお、人に頼るのが苦手という性格的傾向も、親の介護を誰かに任せられない原因の一つです。
親の介護を最後までやりきりたい気持ちを大切にしながら、現実と向き合うには?
ここからは、親の介護を最後までやりきりたい気持ちを大切にしつつ、現実と向き合うためのポイントを3つご紹介します。
それぞれくわしくみてみましょう。
介護のプロに頼る
無理なく親の介護を続けるためには、一人で抱え込んでパンクする前に、介護のプロの力を借りることが大切です。
ケアマネジャーやヘルパー、施設職員などは、あなたの頑張りを否定する「敵」ではありません。より良い介護の形を一緒に探す「チームメンバー」です。
介護のプロたちも、各々の専門知識を活かしながらチームで支援します。あなたも任せられる部分はプロに頼り、自分が担う部分に力を注ぎましょう。例えば、親の精神的な支えや希望の汲み取りは、専門職よりも子どものほうが力を発揮しやすい支援です。
昔の写真を一緒に眺めながらたわいもない話をしたり、好きなテレビ番組を一緒に見たりするだけでかまいません。親子の何気ない時間が、親にとっては大きな心の支えとなります。
親の「希望」と「必要な支援」を分けて考える
親の希望と必要な支援を分けて考えることは、介護を担う子どもの負担を減らすために重要です。
例えば、親が「介護は家族に全部やってほしい」と希望したとしましょう。希望を叶えるために子どもが親をサポートしすぎてしまうと、親のできることが少なくなってしまいます。
結果的に親の自立度が下がり、介護する子どもの負担が増える恐れがあります。
親の自立のために必要な支援は何なのか見極めるのは、介護の専門知識が少ない子どもには難しいことです。ケアマネジャーといった専門職に相談し、親の希望を尊重しながら必要な支援もできる方法を模索しましょう。
自分自身の生活と健康も守る
介護を続けていくためには、子ども自身の生活と健康も守る必要があります。仕事や家庭、自分の体調などを犠牲にし続けると、共倒れになりかねません。
介護は長期戦であり、いつ終わりが来るかわからないものです。無理をしないために、公的なサービスや制度を活用しましょう。
例えば、要介護状態の親を介護する際に、通算で93日間仕事を休める「介護休業制度」が利用できます。休業中に活用できるサービスを調べ、親の介護と私生活を両立するための仕組みを整えるのがおすすめです。
なお、子どもが雇用保険に加入している場合、条件を満たしていれば休業期間中に介護休業給付金が支給されます。介護休業給付金の受給要件について詳しく知りたい方は、こちらも合わせてご覧ください。
「介護の全部」を背負わないためにできること
介護の全部を背負わないためにも、周囲に頼るようにしましょう。
まず、きょうだいや配偶者と親の介護について話し合うことが大切です。話し合う際は直接的な介護だけでなく、経済的支援や情報収集などの分担も決めましょう。分担できると負担が軽くなり、今後について考える余裕も出てきます。
さらに、地域包括支援センターや介護者家族の会など、外部に相談するのもおすすめです。些細な介護に関する悩みも相談できるため、精神面の負担を取り除けます。デイサービスやショートステイなど、介護の休憩を取れる選択肢も教えてもらえるでしょう。
なお、地域包括支援センターや介護者家族の会の連絡先は、住んでいる地域名と一緒に検索するとわかります。
親の介護を誰かに任せることは、親不孝ではありません。周囲の力を借りながら無理せず介護し続けることも、“親を大切にする行為”です。
誰かに頼ったからこそ、親子関係が守られた|体験談
介護を一人で抱え込み、ストレスから親に優しくできなくなることは誰にでも起こりえます。誰かを頼ることで適度に距離ができ、親子関係が守られるのは決して珍しくありません。
ここからは、誰かに介護を頼ったからこそ親子関係が守られた体験談を2つご紹介します。
兄に週末の介護を頼ったケース
まず、別居している兄に週末のみ親の介護をお願いしたケースです。週末だけでも自分の時間を持てるようになり、以前よりもストレスが溜まりにくくなりました。
手伝わない兄への不満も小さくなり、兄との関係性も良くなったそうです。
介護のプロに頼ったケース
次に、親の施設入所を決断し、プロと協力しながら介護するようになった体験談です。余裕ができたことにより、ギスギスした親子関係が改善しました。
夕食時に面会に来て、食事介助をしながら親子の時間を楽しめるようになったそうです。
介護を一人で抱え込み、ストレスから親に優しくできなくなることは誰にでも起こりえます。誰かを頼ることで適度に距離ができ、親子関係が守られるのは決して珍しくありません。
親の介護は「務め」から「選択」へ。介護の形に正解はありません
親の介護は、頼る相手やサービスを柔軟に変えながら続けていくことが大切です。たとえ介護の方法が変わっても、子どもが親を想う気持ちはしっかりと伝わります。
介護される親のなかには、子どもに迷惑をかけることを苦痛に感じる方もいます。そのため、“頑張りすぎないこと”が結果的に親の安心につながる場合もあるでしょう。
「親の介護は子の務め」という思いが強すぎるあまり共倒れになってしまっては、元も子もありません。頼れるところはプロに任せ、あなたの心と体を守ることも大切な介護の一つです。
出典
この記事を監修した人
野崎理香 / 正看護師
正看護師として、がん専門センターおよびリハビリ病院に勤務後、訪問看護の現場に従事。
日々のケアを通じて、「本当は聞きたいことがあるのに、時間に追われて質問できない」という利用者様の声に直面し、その課題を解決するため、介護情報サービス「ケアポケ」の立ち上げに参画。
現場での実体験をもとに、看護や在宅ケアに関する実践的な情報提供と記事の監修に取り組む。

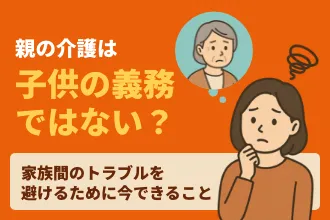






「親の介護は子の務めなので、辛くても頑張らないと」
「親の介護をこのまま続けられるのか不安」
このような思いを抱えながら、親の介護に奮闘している方もいるのではないでしょうか?
介護を通じて親に恩返ししたいという気持ちは、とても素晴らしいものです。しかし、親の介護は気持ちだけでは乗り切れないのも事実です。
この記事では、親の介護は子の務めと強く思うがゆえに起こること、親への気持ちを大切にしながら現実と向き合う方法などを解説します。
親の介護を一人で抱え込み、苦しさを感じている方の参考になれば幸いです。